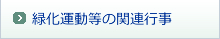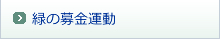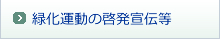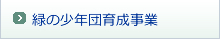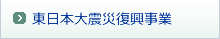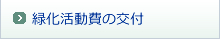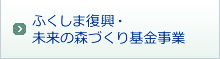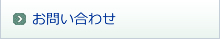「第2回 福島県緑の少年団交流集会」を開催しました。
2015年8月5日
仲間といっしょに過ごす2日間

8月3日、4日(月曜日、火曜日)、大玉村のふくしま県民の森・フォレストパークあだたらにおいて、「第2回 福島県緑の少年団交流集会」を福島県緑の少年団育成協議会、(公社)福島県森林・林業・緑化協会の主催、福島県、福島県教育委員会、関東森林管理局、大玉村、公益財団法人ふくしまフォレスト・エコ・ライフ財団の後援により開催しました。
この交流集会は、昨年度から実施して今回2回目で、緑の少年団同士交流を深めるとともに、様々な体験や研修等を通じて次世代の主役となる森と緑づくりを担う青少年を育成するため、1泊2日の日程で実施しています。
今回の交流集会では、緑の少年団6団29名、引率の先生9名の計38名と前回の3団9名(うち先生3名)を大きく上回る参加者となりました。
交流集会1日目は、開会式(森林学習館・ホール)から始まり、主催者である福島県緑の少年団育成協議会の渡邉裕樹会長が挨拶し、次に、事前に事務局が6団の少年団員を8つの班に分けたグループ毎に集まり、お互いに自己紹介を済ませた後、木工室に移動し、班毎に舞きり式の火起こし道具づくり(火起こし体験)を行いました。その後、場所をサテライトハウスDに移り、テント設営、夕食づくり、夕食、ナイトハイクの順に活動しました。


火起こし道具づくりでは、渡邉会長の指導の下、ノコギリで木材を切ったり、組み立てたり、また火種を発火させる材料となる麻綿を作るために麻ヒモの撚りをほぐして綿状にして、実際に火起こしする体験をしました。子どもたちは出会ったばかりの少年団の仲間とすぐに打ち解けた様子でいっしょに協力しあいながら皆暑さと時間を忘れ、火起こし道具づくり・火起こしに夢中になって取り組んでいました。火起こしに成功したのは、3名程で、先生方も弓きり式で火起こしに挑戦しましたが苦戦している様子でした。この火起こしの体験を通して子どもたちは、ガスや電気を使わず火を起こすことがいかに大変か身をもって感じ、現在の自分たちの暮らす環境がいかに恵まれているかということをよく考える機会になったと思います。




その後のテント設営、夕食づくりでは、福島県キャンプ協会の松前雅明さんをはじめ4名のキャンプ協会スタッフの指導の下(以降、ツリークライミング以外のプログラムを担当)、行い、子どもたちは協力しながらテントを張ったり、カレーの食材を切ったり、バーベキューしたりするなど積極的に活動していました。夕食の準備が終えると、すっかり仲良くなった少年団員同士で和気あいあいとした雰囲気のなか夕食を楽しんでいました。









1日目の最後は、フォレストパークあだたらの敷地内の森の中を班毎に分かれてナイトハイクしました。
辺りは電灯もない夜の森の中を探検するということで、出発する前にロウソクとアルミホイルを使って、自分オリジナルのランタンを一人一人作りました。
普段経験することのない暗闇と人工音が聞こえてこない世界を、月明かりと手作りの灯りを頼りに探検しました。森の中は、虫の鳴き声や川のせせらぎの音が響き渡り、川沿いではあちらこちらでホタルが舞っていました。足を進め、広場に到着すると、フィルムケースに入った塩や砂糖などを舐めて白い粉が何なのかを当てる「白い粉当て」ゲームなどで楽しみ、最後は松前さんを中心に輪となって、童謡“ふるさと”などをみんなで合唱しました。歌い出しで“ふるさと”を知らない子が、「ウサギおいしい?」と勘違いする一幕もございましたが、気にしていた天候も最後まで崩れず無事夜の探検を終えることができました。
夜の自由時間は、入浴後、それぞれのテントで子どもたちだけの時間を過ごしていました。




交流集会2日目は、テントの片付けから始まり、皆で朝食を食べた後、班を大きく3班に分けて森林学習館の周辺でツリークライミングやハンモックの体験、野外ゲームの3つのプログラムをローテーションして楽しみました。




ツリークライミングでは、まずツリークライミング®ジャパンの上條大輔さんをはじめ5名の専門スタッフから、実演を交えてロープを使った登り方と注意点についてレクチャーを受けました。レクチャー後、ヘルメットやサドル(安全帯)を装備した子どもたちは、森林学習館の前に太く立派にそびえ立つアカマツの枝に垂らされた12本のロープに取り付けられ、教わったセーフティー(ストッパーのためのロープを結ぶ作業)を作りながら、脚と腕を交互に動かし上へ上へと登っていきました。最初は皆ぎこちない動きでしたが、中にはすぐにコツを掴んで、キリンの身長程の高さ5メートルを超える高さくらいまでスイスイと登っていった子もいました。また登るのに夢中で気付いた時には、あまりの高さに驚く子もいました。体験終了後には、全員にツリークライミング体験記念の認定証が配られ、受け取った子どもたちは、皆、顔に汗をにじませ達成感でいっぱいの表情していました。




ハンモックの体験では、3種類(布タイプ、網+固定木タイプ、網タイプ)のハンモックを使って、森林学習館の周辺に生えている木々にそれぞれ取り付け、各々自由に楽しんでもらいました。最初に「ハンモックをやります。」と号令をかけたときに、子どもたちは頭にはてなマークが浮かんだような表情でしたが、「ハンモック」という言葉を初めて聞いたという子がほとんどでした。それにもかかわらず、子どもたちは、自分たちで楽しみ方をすぐにみつけ、唯々ゆったりしてみたり、バランスをとるのに夢中になってみたり、ハンモックから落ちそうになるくらい揺らしてみたり、自分たちの様子を見て「えだ豆」を連想してみたり、思い思いに楽しんでいました。




野外ゲームでは、「フープリレー」、「バケッツボール」、「鶴折り」、「林間立木取り」、「UFO着陸」といった、どのゲームもフープやボール、ブルーシート、ロープなど簡単な道具を使い、みんなと協力しないとできないゲームばかりでしたが、どの班もチームワーク抜群で、真夏の青空の下、元気に遊んでいました。





交流集会の最後は、森林学習館のホールで反省会を行いました。
反省会では、班毎に印象に残ったことや楽しかったことなど2日間を振り返り、班の代表がまとめて発表しました。
「自分たちだけで料理を作ったのは初めてでした。」
「テントを初めて張りました。」
「ツリークライミングとても楽しかったです。もっとやりたかったです。」
「お友達がたくさんできて良かったです。」
と、子どもたちはとても充実した表情で感想を述べていました。
反省会後、参加者全員に昼食の弁当を配布し、2日間にわたる交流集会が無事終了しました。
今年度、正式に全国植樹祭の本県開催が決定し、今後、緑の少年団の役割が更に重要になってくることから、これまで以上に青少年育成活動を支援・推進していかなければなりません。
次回も子どもたちに有意義な時間を過ごしてもらうとともに、参加して良かったと思えるような交流集会にしていきたいと思います。


新聞記事掲載:福島民友(2015年8月7日付、12面)